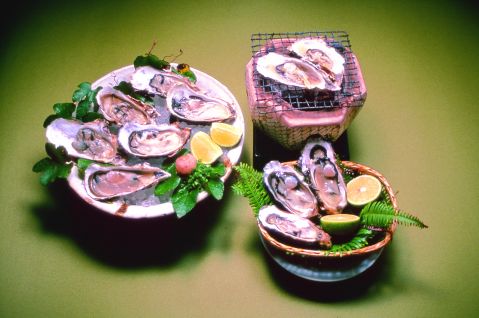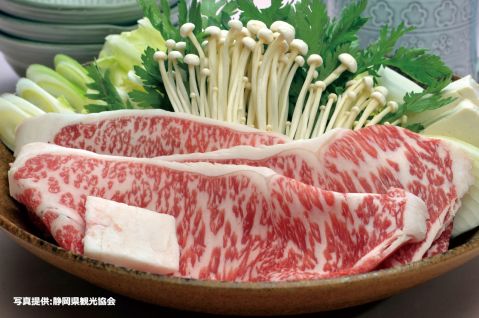ご当地魚介・海鮮料理
宮崎県
魚介・海鮮料理
宮崎かつおうみっこ節
「宮崎かつおうみっこ節」は、宮崎県で水揚げ、または宮崎県のかつお一本釣り漁船が漁獲したカツオのみを原料に使用し、日南市漁業協同組合女性部水産加工グループが手造りで謹製した逸品で...